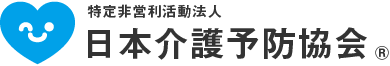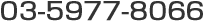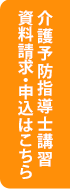高齢者には運動の習慣を積極的につけさせることが奨励されています。筋力の維持、寝たきりの予防など、基礎体力を少しでも維持していくのが目的です。
しかし、あまりハードな運動ではもちろん続きません。高齢者にぴったりの運動やレクリエーションにはどんな種類があるのでしょうか。
高齢者が運動をする目的とは
高齢者が運動をする目的は、身体機能の維持の他、ストレス解消や認知機能低下を予防することです。筋力や基礎体力、免疫力といった生きる力が年々衰えていく中で、運動することは今ある機能を少しでも維持することにつながります。そうすることで、様々な疾患を予防したり、ケガによる骨折や転倒を防ぐことが可能になります。
また体を動かすと血流が良くなり、病気だけでなくストレスの発散や精神安定にも一定の効果が見られます。運動は脳にもある程度の刺激を与えるので、もの忘れや認知症の予防にも役に立つと言われています。このように考えてみると、高齢者が運動するデメリットがもはや思いつかないほどです。
運動は継続して行うことが大切です。本人の体力に見合った内容と、無理のない範囲でできるところから始めていきましょう。
高齢者向けの運動やレクリエーションで実際に行われているもの
高齢者向けの運動やレクリエーションで、実際に施設などでよく行なわれているものを一部紹介しましょう。自宅でも、また車いすに乗っていてもできるものがあります。
全身を使う
誰かに新聞紙を広げて持ってもらいます。新聞紙の目の前に立ち、それに向かってパンチやキックをして破るゲームがあります。思い切って破ることでストレス発散と全身運動を兼ねており、また新聞紙に集中することで注意力を養えます。
体幹を鍛える
床に大小いくつかの得点が書かれた紙を置き、その上に風船をキックしながら乗せていきます。足で蹴ることで下半身にはもちろん、床上の紙の的を狙うためバランス機能を高める効果にも期待できます。
下肢の機能を維持する
幼稚園や保育園でもよく遊んだ、足を使ったじゃんけんは高齢者の下肢機能維持に大変役に立ちます。足を揃えるのがグー、左右に開くのがパー、前後に開くのをチョキといったように下半身を動かし、筋力低下を予防します。
なお動かし方を工夫すれば座ってでも行なえますが、その場合は足を床から浮かせると腹筋力をつけられます。
簡単にできるシニア向けの運動いろいろ
シニア向けの運動は、身近なところでできるものが数多くあります。体が元気なうちに習慣付けておくことをおすすめします。ポイントは継続。そのためには体力に合わせて続けやすいものを行なうこと、そしてその効果を実感させるのが肝心です。
比較的手軽に行なえる、人気の運動とその目的を紹介します。
水中ウォーキング
プールに入って水の中をゆっくりと歩く運動です。目的は心肺機能を向上させ、全身の血流をよくすること。血流が良くなると栄養が行き渡りやすくなるため、食欲の増加や意欲の向上など、心身ともに好影響が期待できます。
筋力トレーニング、バランス訓練
シニア向けの筋トレは重いダンベルを持つようなものでなく、片足立ちや足を上げ下げするなど、日常生活で簡単にできる内容です。筋肉量を増やしたり、筋力を強化することで骨折などのケガから守ります。
ストレッチング
足首や手首の関節を回したり、腕や足を伸ばすストレッチです。筋肉の柔軟性を高め、関節の動きが固くなるのを予防するので転倒によるケガの防止にも役立ちます。
ウォーキング
近所の散歩程度から始め、慣れてきたら少しずつ距離を伸ばしてみるなど工夫しましょう。骨を丈夫にする他、内臓の働きを良くして食欲を増やし、さらにリラックス効果にも期待できます。
高齢者が運動するとどのような効果が得られるのか
高齢者が運動を行うと、たくさんの良い効果が表れます。身体機能にとっては筋力が向上し、転倒や骨折などケガの予防に役立ちます。また、血流がよくなるため内臓の働きも活性化するので食欲が増進し、さらに腸内環境が良化し免疫力を高められます。生活習慣病をはじめとした、各種の疾患の予防にもつながります。脳に適度な刺激を与えることで、もの忘れを防ぎ、精神を安定させる効果もあります。
介護が必要になる原因の1位が病気、2位が認知症です。寝たきりにならないためには原因の排除が大切、そのためにも定期的な運動の習慣はとても重要なのです。
まとめ
高齢になると、筋力や免疫力などあらゆる身体機能が低下していきますが、その予防には運動やレクリエーションが1番です。ポイントは継続させること。そのためには体力に合わせた無理のないメニュー作りが大切になります。
紹介した運動の他にも、たくさんのバリエーションがありますので、本人の体力や得意なことを考慮しながらぜひ試してみてください。運動をすれば体力の増進の他、認知機能アップやリラックスにも効果を発揮しますので、ぜひ習慣付けましょう。